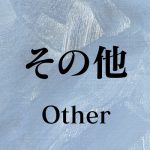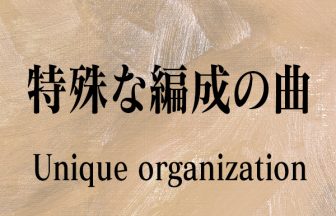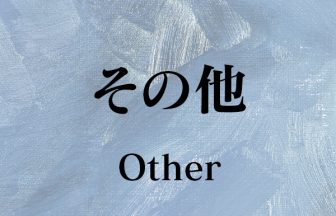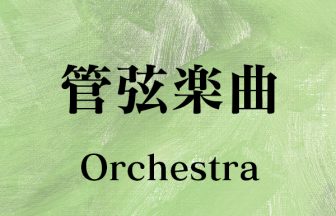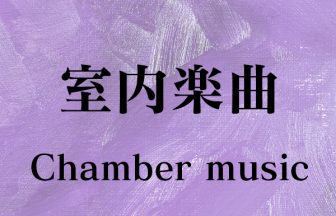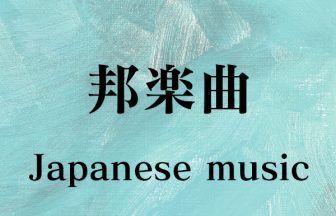この「市川市立新浜小学校吹奏楽部応援のページ」をご覧になった皆様より多くの感想を頂き心より嬉しく思っています。7月から8月にかけて吹奏楽コンクールシーズンに入り指導や審査などで自宅を留守にする機会が多く,締切にも追われ(今も悪戦苦闘中)すっかり当ページを更新するタイミングを逃していました…。 長い間,更新が遅れてしまいご迷惑をおかけしました。
小学校のコンクールのシステムをご存じですか?
私は新浜小に関わって始めて吹奏楽コンクール(全日本吹奏楽連盟主催)の“小学校部門”についてのシステムを知ったのですが,小学校には中学生・高校生のように全国大会が無いそうです。新浜小が応募した“小学校A部門”というのは,まず「千葉県大会」があり,金賞を受賞した中で6団体が「東関東大会」へ進み,この大会で金賞を受賞した中で2団体が最後の「東日本学校吹奏楽大会」に進むことができるのです。すなわち「全国大会」というのが無い代わりに「東日本学校吹奏楽大会」として日本半分の学校が参加する大会があるのです。尚,この「東日本学校吹奏楽大会」というのは昨年から実施されているとか。
2002年7月28日「千葉県吹奏楽コンクール 小学校A部門」
いよいよ千葉県大会の当日になりました。何度も練習に顔を出して子供たちの様子は見たものの,当日になると親のような気持ちで何かと心配になるものです。ましてや自分の作品ということもあり私自身も審査されるような…。朝一番から作曲家の神長一康さんと共に客席で他の学校の演奏を聴きました。私も神長さんも中学・高校生の県大会の基準は判りますが,小学生の基準は未知の領域。頑張って演奏しているのを見ると,それだけで思わず褒めてあげたくなる気持ちになります。どの学校も大変力のこもった演奏で指導されている先生方の熱意が伝わるようでした。なかには中学生・高校生が演奏するような難曲を選曲し見事に音楽を創り上げている学校もあり,小学生の吹奏楽のレベルに驚くばかりでした。
ついに新浜小の出番がやってきました。昼過ぎということもあり客席もほぼ満席。ホールには益々緊張感が漂います。新浜小の子供たちが舞台に出てきます。すると客席より“おおっ!”という声が!!まだ舞台はセッティングも終えていませんが,入場する子供たちの言い知れぬ存在感に既に聴衆は魅了されているのです。練習を思い出すと田川先生は入場する際の歩き方にも徹底した指導をされていた。子供たちの入場する姿勢には既に「私達の音楽を聴いてください」という誠実な真心が表れているのです。細かく意図された打楽器の配置,扇のように舞台に広がる美しい椅子の並び。暗譜をして田川先生の指揮の合図を待つ子供たち。音を出さずにして会場には新浜のオーラが広がっているのです。演奏が開始されるとホールには海の情景が広がり誰もがただじっと子供たちを見つめているのです。やさしくベールに包まれるようなサウンド。これが本当に小学生なのでしょうか。少々,惜しい箇所(作曲者だからこそ判る部分です)もありましたが本当に素晴らしい演奏でした。もはや評価などは関係なく感動的な瞬間でした。
あれだけの演奏をするのだから当然,夏休みも厳しい練習が続くと思っていましたが新浜小にはちゃんと夏休みがあるのです。夏休みの終わりには千葉の岩井海岸で合宿(主に遊び)もあり,9月の二週目までは全くコンクールの練習をしないそうです。ということで私は一ヵ月ほど子供たちには会う機会がありませんでした。
一方この時期の私は8月31日に開催された市川市民ミュージカル「いちかわ・真夏の夜の夢」の通し稽古に立ち会う機会が増え,また他学校吹奏楽部への指導なども入り各々別の行動をとっていたのですが,7月半ばに出版された『教育音楽―小学版』〔音楽之友社〕の記事を読まれた方やコンクールを聴かれた方々などからご感想を頂き,常に頭は新浜小のことに触れていました。この『教育音楽―小学版』の記事というのは新浜小の顧問である田川伸一郎先生が着任してから毎月連載している【追いかけよう夢を!子どもたちと共に!!~吹奏楽指導奮闘記】のことです。この連載では三年前より,新浜小の吹奏楽部を新たに創り上げた苦労や工夫を語っているもので,今回(第26話)の記事では私との出会いや《輝きの海へ》を私に依頼した経緯が詳しく書いてありました。
9月11日 久々に練習へ
「コンクールの練習を開始しました」というご連絡を田川先生より頂き早速遊びに行くことにしました。この日はちょうど富山から千葉に帰る日だったので羽田から新浜小へ直行しました。富山に行ったのは富山ミナミ吹奏楽団の全日本吹奏楽コンクール三年連続出場を記念した作品を書くためです。「富山の風景を題材に!!」ということだったので北アルプスへ取材旅行へ行っていたのです。一昨日に立山の地獄谷の大変長い階段を登ったせいか足を始め身体のいたるところが筋肉痛。くたくたの状態で新浜小の体育館へ入りました。
この日は東海大学付属浦安中学・高等学校吹奏楽部の約50名の皆さんが見学に来ていました。以前も東京学館浦安中学・高等学校吹奏楽部の皆さんが見学にいらしていましたが,新浜小の練習は高校生にも大変刺激になるようです。こうした交流が増え互いに向上していくと良いと思いました。練習が始まり驚いたのは高校生だけではありませんでした。一番驚いたのは作曲者の私です。7月の千葉県大会と全然演奏が違うのです。7月の時点でも丁寧で素晴らしいものでしたが,今の演奏は全く子供を感じさせず細部まで研究しつくされた音楽なのです。正直,以前は(作曲者だからこそ要求したくなるような)微妙なニュアンスやダイナミクスの幅などで惜しい!!と感じられる場面がありましたが,今は欲求不満の箇所は全く無く,更に信じられないような表現力が備わっているのです。それはまさに私が思い描いていた音楽そのものなので驚きです。田川先生はスコアを深く探究し,私の意図や気持ちを心から理解してくださったのです。子供たちも完全に楽譜を暗譜し小節番号を指示しただけで,どんな箇所からも演奏できるようになっています。しかも田川先生が指揮をしなくてもアンサンブルのように互いの呼吸のみで最初から最後まで一切のズレを生じさせず演奏できてしまうのです。この奇跡的な状況を目にして(北アルプスでの)身体の疲れは一瞬で吹っ飛びました。練習が終わり東海大学付属浦安高等学校吹奏楽部の皆さんも何かを感じたのでしょう。田川先生のご厚意もあり新浜小の音楽室を借り,高校生たちがミーティングを始めました。練習を見学して感じたこと,今後の自分たちに今日の刺激をどう生かすのかなど夜遅くまでディスカッションが続きました。私は中学・高校生の演奏を聴くことはあっても,このような長時間に渡ってのミーティングを聞く機会はまず無いので黙ってじっと見学させて頂きました。私自身も多くのことを勉強させて頂いた一日でした。
9月15日「TBSこども音楽コンクール 千葉県大会」
名のごとくTBSが主催するコンクールで吹奏楽部門の他にオーケストラや重奏,合唱などの分野も同時開催されています。このコンクールは予選としてテープ審査があり,テープ審査に合格した新浜小は習志野文化ホールで開催された千葉県大会に出場しました。一週間後に控えている東関東大会(吹奏楽連盟主催)のホールとは構造や音響も全く違うので,練習にあたって田川先生はだいぶ苦労をされているようでした。が,この日も見事な演奏をしてくださいました。司会を務めていたTBSアナウンサーの驚きの表情が印象的でした。
《輝きの海へ》についてのお問合せ,ご感想はこちらまでお願いします●